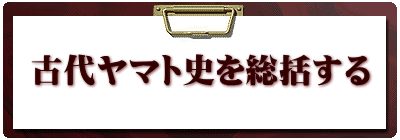 H28.7.9 追記挿入の 古代ヤマト史総括-Ⅱです。 H22.1.8日経新聞茶臼山古墳の記事を読んだ後、H22.1.11「大胆古代ヤマト史」を掲載しました。 その後、NHK-TVで「邪馬台国を掘る」が放映されたりしましたので、古代ヤマト史総括-Ⅰをまとめました。仕切り線の下になります。 並行的に、H25.9.4 「古代ヤマト史天皇系譜」において、 崇神天皇(10)〜継体天皇(26)の系譜 と 中国の諸史書(後漢書、魏志倭人伝、宋書)での九州倭国についての記載 とを 私の勝手な古代ヤマト史により、ジョイントしてみました。 その後も、古代ヤマト史に掲載を重ねてきましたが、他方 九州地区への旅行機会にも恵まれました。 H25.2.25 宇佐神宮 H25.7.2〜4 壱岐・対馬旅行 で、壱岐の原の辻遺跡 H28.1.29〜31 九州邪馬台国ツァー(ジパング倶楽部主催) H28.5.31 吉備王国の謎ツァー(ジパング倶楽部主催) 特に、H28年1月末九州邪馬台国ツァーは、邪馬台国は、九州にあったことを確認させる画期的旅行になりました。 更に、H28年5月に全国邪馬台国連絡協議会にお誘いあり、その近畿地区会合で魏志倭人伝を読むことになり、その基礎勉強の1つ として、50年前の著作 宮崎康平著「まぼろしの邪馬台国」を改めて読み直し、それの集約と倭国30国配置を私の解釈でまとめ、掲載 しました。 宮崎康平著「まぼろしの邪馬台国」の見方、上記ツァーでの見聞、更に粗い古代ヤマト史追加想定を付加して、古代ヤマト史総括-Ⅱ としたいと思います。 ①倭国という表現は、中国からみた、弥生時代の九州ヤマトを指す表現で、日本はその頃国家意識は無く、クニ=小国家 でないか。 ②九州では、1〜2世紀に多くのクニが離合集散を繰り返していた、この中、壱岐に近く、やや優勢にあった奴国が後漢に遣使を出し 「漢委奴国王」の金印 を確保するまでになった。 この倭国の内乱過程で押し出された崇神軍が、東征し、出雲・吉備勢力と争い、講和した上、ヤマトに入り長髄彦命と争い勝利した。 ③弥生中期(1〜2世紀)、九州ヤマト・出雲・吉備・畿内ヤマト・尾張 各地に鉄生産能力が行きわたり、それぞれ争い、融和を繰り返し 稲作技術向上もあり、独自の文化圏を形成したと思われる。 中でも畿内では出雲勢力・吉備勢力の共立で力をつけヤマト王権が、文化・武力の吸い上げ効果と地政学上の優勢 を生かし、 近畿一円〜東海を制覇し、各出身地をベースとした豪族共立の王権となった。 ④九州では、奴国小国家連合と邪馬台国小国家連合の2グループに集約され、次いで卑弥呼率いる邪馬台国が、邪馬台国大連合 (魏志倭人伝の倭国30国のうち、狗奴国を除く)を形成した。この連合に入らない狗奴国が南にあり、邪馬台国大連合との対立が 顕著になってきた。卑弥呼は、これに対抗すべく、魏帝に朝貢し、「親魏倭王」の称号 を得て、魏を後ろ盾にしようとした。 …これは、主として宮崎康平著「まぼろしの邪馬台国」に準拠します。尚、邪馬台国の所在については、諸説ありますが、 九州地区であることは、大勢になっています。私も九州邪馬台国ツァーに参加して確信しました。 ⑤しかるに、3世紀に入って、力を付けてきた 畿内ヤマトが、九州ヤマト=邪馬台国大連合 と 熊襲=狗奴国を抑えようとして 神功皇后が九州征討に向かい、一応勝利した。そこで邪馬台国連合は、崩壊し、卑弥呼は、纏向宮殿に移った。 ⑥その後、ヤマト王権は、ヤマト・河内に拠点を置き、九州〜東海の一応全国制覇した。 この過程に興味があるが、日本書紀、古事記は、まともな記述を避け、中国サイドにも、倭の五王以外の記録が無い様ですが、 各地に巨大古墳を作れるまでに、国力がついてきたことは、間違いない。ただ、巨大な前方後円墳の目的は、威力顕示よりも、 環濠の稲作用 水利用途がメインではないかと思う。畿内の宮内庁管轄前方後円墳は殆ど、天皇陵として、天皇名がついて いますが、いずれも天皇名との対応は、確認されていない。 ⑥継体天皇の528年に筑紫磐井の乱があり、物部氏がこれを鎮圧したと聞くが、この時期、天皇と物部氏を含めた豪族の関係はどう であったのか、つぎの機会に考えたいと思います。 以下当初書きました (H25.8.12〜H26.6.19掲載) 古代ヤマト史総括-Ⅰです。 mtd付 本HP掲載当初は、飛鳥地区(明日香村とその周辺地区)に重点を置き、なんとなく天智・天武天皇関連が中心で、系図を作成 したり、飛鳥時代の年表を自作して、歩いた記録写真を掲載していました。 しかし、飛鳥・ヤマトを歩きまわっているうちに、藤原氏に牛耳られてゆく、飛鳥の歴史よりも、その前のヤマト王朝成立過程が、 実に面白そうで、興味がもてるということがわかってきました。これを私は、古代ヤマト史と表現しています。 教科書で学んだ日本書紀・古事記は、藤原氏の都合で歪められたもので、実際は、ロマンあふれる想像と創造一杯の世界が そこにあるということがわかりました。 ヤマトを歩いて、そこで写した写真をその都度掲載している過程で、実に断片的な、勝手・恣意的な「古代ヤマト史」を掲載して きましたので、ここでちょっとだけ整理してみたいと思います。 (H25.8.12第1次掲載) 従い、このページでは、今まで掲載してきた「古代ヤマト史」の関連ページをラベルリンクで結び、整理してみます。 ラベルリンクは、該当箇所に直接行きますので、戻る場合は、インターネット画面左上隅の左矢印 (他のページに迷いこんで、戻れなくなったら、「表紙に戻る」で表紙indexに戻り、このページ「古代ヤマト史総括」に入って下さい) 私の大胆古代ヤマト史は、原則、現地に行って想像をたくましく創造したもので、いずれもどこにも無いユニークなものですが、 特に、下記の (2) (6) (7) が自分でも面白いと考えています。
H25飛鳥・ヤマトのページに
|