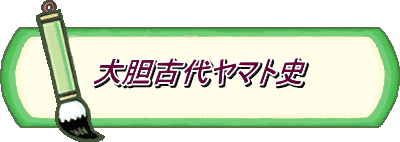 Chausyamakofun H22.1.8 奈良・桜井茶臼山古墳について、興味深い記事が出ていました。 (記事は、同日付 日経新聞朝刊によるものです) 箇条書きでポイントを記します。 1.「卑弥呼の鏡」との見方がある三角縁神獣鏡の破片が大量に出土した。 2.今回三角縁神獣鏡が26面の鏡片が確認された。 3.そのうち1つの鏡片に「是」の字が刻まれていた。 4.この字体が、蟹沢古墳で出土した魏の年号「正始元年(240年)」の銘鏡と字体・凹凸 が一致し、同じ鋳型で制作された兄弟鏡とわかった。 5.この字「是」は、「氏」に相当し、作者とみられる「陳」…魏志倭人伝の筆者陳寿… の次に刻まれていた。 6.正始元年は、卑弥呼の遣使が魏から銅鏡100面を持ち帰った年 7.この銘を持つ鏡が初期ヤマト政権の中心地で出土したのは、初めて。 8.鏡の破片は、331点出土し、他の古墳から出土した700面の鏡をレーザー光線 で細密に3次元計測したデータベースと照合し、厚み鋳造状態を分析して、 個体数と鏡の種類を判別した。 9.復元した、鏡の半数は、20cmを超え、最大は、40cm前後の?製内行花文鏡 は平原1号墓の?製内行花文鏡46.5cmに匹敵する大きさ( 注 : ?製=国内製) 10.鏡が細片であったのは、埋葬時破砕したのではなく、盗掘者が割ったとみられる。 注 : 茶臼山古墳は、200mの大型前方後円墳で、1949年石室の発掘で、鏡片53点 など出土していた。昨年60年ぶりに、橿原考古学研究所が再発掘した。 茶臼山古墳の被葬者は以前から、大王級とみられていたとのことですが、 この出土結果に伴い、白石太一郎氏(大阪府立 近つ飛鳥博物館館長)は 「被葬者は、文物の入手や分配の機能を一手に握っていた人物では」 と話されています。(日経新聞) H23.1.22 各紙に纏向遺跡(纏向宮殿跡)から、食べた形跡の無い、祭祀の供物とみられる タイなどの海水魚、こめ、麻などの種子等等9,800点をみつけたとの発表(桜井市教育委員会) があったとの、記事掲載あり。(NHK-TVでも前日21日晩のニュースあり) 更に土壌の花粉を分析するとモモの花粉が大量検出されたので、「祭祀用のモモを周辺で栽培 する畑が広がっていたのでは」とのこと 以下、私の大胆古代ヤマト史追加です。…H23.1.22 '1.卑弥呼は、祈祷師として、邪馬台国の女王であったことが、通説であり、纏向に来た(神功皇后 が九州征討の後、つれ帰った)卑弥呼は、纏向宮殿で、祈祷に専念した。 '2.祈祷に際し、ヤマト朝廷に与した(服した)全国の氏族から供物が届けられた。 '3.神功皇后・卑弥呼死去後、それぞれ茶臼山古墳と箸墓古墳に葬られ、この宮殿は、打ち捨て られたと思われる(応神天皇…15代…の時代)
尚、これに関連して、H23年1月纏向遺跡出土遺物とそれに伴う追加記載を別ページに掲載しました 平城京北にある神功皇后陵と成務天皇(13)陵を見てきましたが、茶臼山古墳より、 小さくみえます。(H22.1.10) 神功皇后陵…「神功皇后狭域盾列池上陵」と書かれています。 RO写真  成務天皇(13日本武尊と兄弟)陵 RO写真 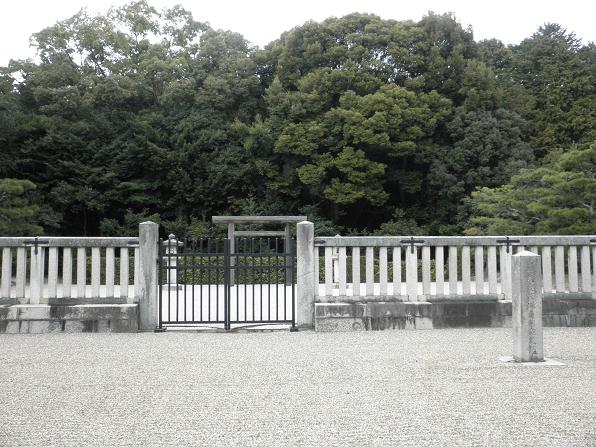 神功皇后陵に行く手前に称徳天皇(48)陵がありました。RO写真 称徳天皇は、聖武天皇の子で、孝謙天皇(46)・称徳天皇(48)と「重祚」の女帝(道鏡の時代)  茶臼山古墳のページに戻る  |