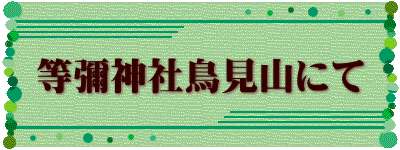 古代ヤマト史3 H25.4.9 古代ヤマト史3 H25.4.92年前に等彌神社に行ってから、構えは、さして大きくないのに、由緒が深そうな、神社として、惹かれるものがあります。 この日、帰りに梅田でメールチェックをするつもりで、バッグにパソコンを入れていきましたので、245m高さの鳥見山に上がる のに結構疲れ、時間がかかりました。 等彌神社入口の表示をRO写真で  鳥見山登り口の表示、霊畤まで約1kmあります  一応、鳥見山山頂に霊畤(レイジ…まつりのひろば)があります。(RO写真)  上の写真の左にベンチがあり、そこに腰掛けて (1)ここの鳥見山と宇陀榛原の鳥見山との関係 (2)このヤマト地区にある初期前方後円墳との関係 について、妄想しました。その後の追加妄想も取り込んで以下書き並べてみます。 (1)2つの鳥見山 1.宇陀榛原の鳥見山は、崇神軍が、宇陀城山に陣する長髄彦命をこの鳥見山と烏ノ塒屋(カラスノトヤ)からと挟み撃ちで 攻めるに際し、この霊畤で軍議を開き戦勝祈願をしたものと推定できる 2.等彌神社の鳥見山霊畤は、この故事に因み、後の成務天皇(13)が、日本武尊に東日本制圧を命じる等、ヤマトを治める 場としたものでないか。この周辺に「跡見」「外山」「等彌」「鳥見」と、字は違うも、いずれも"トミ"と読める地名があるが、鳶が 上から地域を導き支配するという意味があるのでは、ないか。…奈良青垣出版の「纏向遺跡と桜井茶臼山古墳」のなかに 日本書紀でトビに関する記載が2回あると書かれている。 神武天皇(崇神天皇)を導いたとされる八咫烏は、鳶のことではないか。 zenpoukouenfun (2)ヤマト地区にある初期前方後円墳との関係 1.鳥見山の霊畤に部分は、政治の場になり、その前方一段低くなって、命令を受ける軍・行政が控えることになる。 従い、一段高い霊畤の部分が後円部となり、一段低く前方部となり、前方後円墳の原型となった。 すなわち、初めは、天皇の治世の場であったものが、天皇が薨じると、そこに葬ることができ、今に残る前方後円墳となる のではないか。 近畿の前方後円墳の方向は、マチマチであるも、棺の方向は、全部が北枕と聞くのは、前方後円墳は、最初はお墓として 造られたものでないことを示唆している。 2.稲作水田が開発されていくに従い、貯水ニーズ大きくなり、周囲の土を掘って、中央に盛り土して、時の天皇在世中は、 盛り土箇所で政治を行い、周囲の掘った部分に貯水し、水田に水を供給すると共に、お濠として、外からの防御を兼ねる。 3.崇神天皇陵(崇神天皇を祀るかどうかは、不明であるが)は、龍王山の麓できれいな水を湛えているが、この辺りに、部落 周囲を水路で囲み、給水機能と外敵防御を兼ねた集落がある。 4.応神天皇・仁徳天皇とヤマト王権が強大になるに伴い、時の天皇の権威を誇示すべく、在世中に自分の治世の場を作り、 そこで政治を行い、天皇薨去とともにそこに埋葬され、古墳となったもので、後の天皇が、前天皇のために1から巨大古墳 を作ったものでは無い。 5.茶臼山古墳は、そういう意味で、神功皇后が仲哀天皇に代わり、ヤマトを治めた場であり、そこに葬られたのではないか。 6.私の仮説で、邪馬台国から来た卑弥呼は、纏向宮殿に住まうも、政治を行ったわけでは無いので、神功皇后が別の場 (すなわち箸墓古墳)に埋葬したのではないか。 7.巻向地区には、小さい前方後円墳が数多く見受けられるが、集落毎に貯水池を掘り、土を盛ったもので、必ずしもお墓として 作ったものでは、ないのでは、と思う。 8.後世の高松塚古墳、キトラ古墳は、最初から、お墓として作られ、南側が盗掘口となっているが、いずれも天皇のものでなく 政(まつりごと)とは、ほど遠い造りである。 (付)日本書紀で"神"の諡がつくのは、神武天皇、崇神天皇、神功皇后、応神天皇の4人だけであり、この4人がヤマト王権の キーマンといわれますが、私も、後のお二人が、特に重要な役割・実績を果たしていると思います。 このことに関し、又、稿を改めたいと思います。 H25年飛鳥・ヤマトのトップページに |