
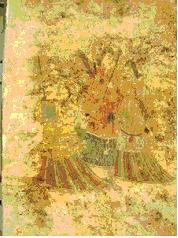
平成19年8月3日
高松塚古墳壁画の変色劣化について
奈良県高市郡明日香村
西田 輝彦
平成19年7月に高松塚古墳の解体後始めて、壁画が文化財関係者及び報道陣に公開された。
壁画は全面に酷く褐色に変色し、発見当初のすばらしい極彩色壁画は失われていた。
古墳発掘当初の昭和47年には図1左のように、壁画は極彩色の鮮明で見事なものであったが、
平成18年9月には図1中のように変色・退色とカビ被害により酷く劣化し、解体し修理施設に
搬入された。
しかし、壁画の劣化はその後も進み、わずか8ヶ月後の平成19年5月には図1右のように、
壁画は漆喰が乾燥して所々にめくれ上がり、飛鳥美人は全面が酷く褐色になり、白虎は退色
して殆ど消失していた。壁画の褐色化は徐々に進んでいたが、特に最近酷くなっている。

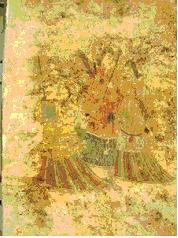
図 女子群像 左:昭和47年、中:平成18年9月(読売新聞)、右:平成19年5月(文化庁)
「特集 高松塚光源」(奈良新聞)等に古墳発掘時石室の一部に木の根が
あったが、全く虫やカビがおらず、出土した銅鏡に金属光沢があり、壁画が
極めて鮮明であり、漆喰の破損がなかったと報告されている。古墳は鎌倉時代
に盗掘されたにもかかわらず、このように1300年間にも亘って壁画が良好に
保存されたのは、発掘前の石室が低酸素の状態に保たれ、カビも生えず、漆喰
の劣化剥落も生じなかったためと考えられる。古墳発掘後、石室内へ大気の酸素が
流入し、壁画の顔料が酸化され、変色・退色したと推測される。
高松塚古墳解体前の石室周囲は地下水が多く、石室内の湿度及び漆喰の含水率測定によると、
湿度は年中98〜100%と高く、漆喰の含水率は15〜25%、飽和度80%以上と高かった。
壁画の褐色化は徐々に進んでいたが、最近特に褐色化したのは、地下水に溶けている炭酸
水素第一鉄Fe(HCO3)2が大気の酸素に酸化され、褐色の水酸化第二鉄Fe(OH)3が析出し、
水分が蒸発して、壁画面に凝縮したためと推測される。さらに乾燥され、水酸化第二鉄
Fe(OH)3が水分を失くしてオキシ水酸化鉄FeOOH(水和酸化鉄Fe2O3・H2Oと同じ)に
変化し酷く褐色化した。
古墳発掘後、地下埋設極彩色壁画の保存技術が未熟で、科学的調査、検討が充分行われず、
石室に大気を入れ、古墳に空調施設を付設して前室の温度と湿度のみの管理を行った。
また、前室の工事に欠陥があり、虫やカビの侵入路になっていた。この結果、壁画顔料の
酸化と地下水の鉄分の酸化による壁画の変色・退色劣化と二酸化炭素による漆喰の劣化、
及びカビの発生が急速に進んだ。
西田技術士事務所 西田 輝彦
昭和13年生まれ 九州大学工学部機械工学科卒業 日立造船、住友電設OB
住 所 :奈良県高市郡明日香村
業務内容:省エネ、発電、空調、工場設備、工事監理、技術鑑定、環境
資 格 :技術士(機械/原動機、総合技術監理)、エネルギー管理士、